- TOP
- JMAソリューションニュース「HRトレンド」
- 成果につながる 研修活用ノウハウ
- やりっぱなしにしない研修活用術! [研修後]編②アンケートを最大限に活用する
人気タグ一覧
公開日 : 更新日 : やりっぱなしにしない研修活用術! [研修後]編②アンケートを最大限に活用する
研修の最後にアンケート記入の時間を設けるというのが通例になっている企業も多いと思います。ただ、通例としてアンケートを取ってはいるものの、それが活かされてないというケースもあるのではないでしょうか。参加者の立場であれば、「早く仕事に戻りたいのに、面倒だな」と感じたことがある人、研修企画者の立場であれば、「どれも変わりばえのしない回答ばかりで報告書の作成がむずかしい」と感じたことがある人もいるかもしれません。そもそもアンケートは「取るべきもの」なのでしょうか?改めて、研修後アンケートの目的はどこにあるのかということを考えてみましょう。
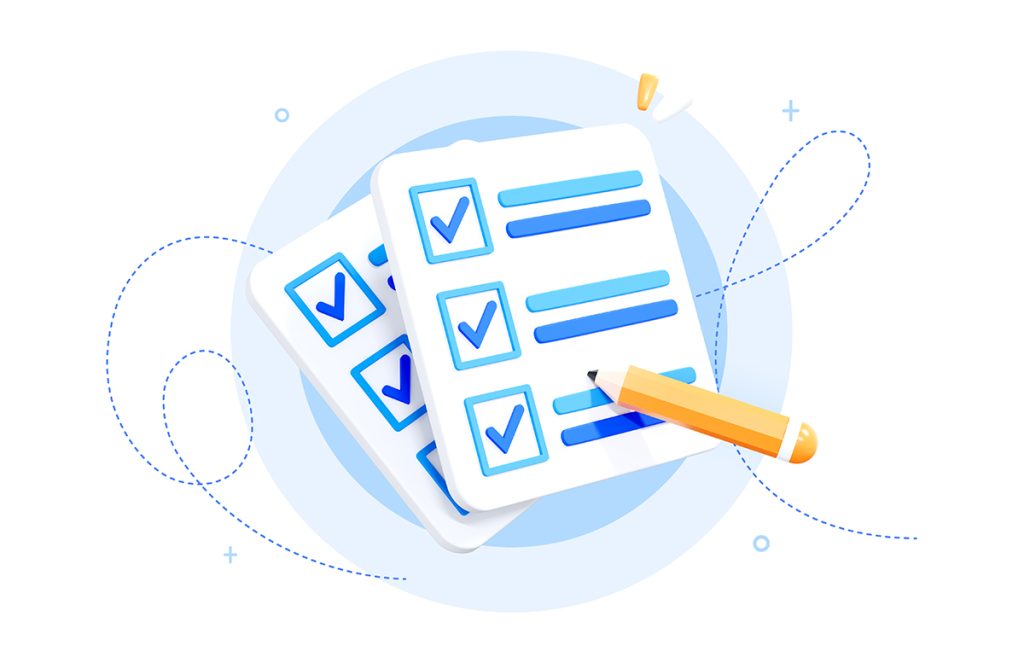
研修後アンケートの利点とは
何となく通例として実施されているケースも多い研修後のアンケートですが、実はアンケートというデータ収集方法には、本来は多くの利点があります。
1 研修の有効性の確認、改善点の抽出ができる
研修の内容が現場のニーズに合致しているかという点は、アンケートを行うからこそ確認できることです。得られたデータから、研修テーマの変更、講師や外注会社の再考など、改善点を抽出し、研修内容のブラッシュアップにつなげていくことができます。
2 研修実施部門の経営貢献度が測定できる
人材開発部門は、企業の中でも重要な核をなしているにも関わらず、ともするとコストセンターとして扱われ、携わる人の評価が正確に行われないことが起こり得ます。研修後アンケートを実施すれば、研修実施部門の貢献度を見える化することができ、納得感のある評価が可能になります。
3 学んだ内容の振り返り、定着を促進できる
研修後アンケートは、様式を工夫することで、アンケート記入までを研修の一部のように設計することができます。学んだ直後に研修での学びを言語化することは、定着を促すことにもつながるからです。特に若手を対象とした研修などでは非常に効果的な手法であり、この場合、具体的なゴールを自分で設定/宣言してもらい、アンケートは後日返却するというのも効果的です。
そもそも研修成果はどうすれば測れるのか?
今回は、主に1の「有効性の確認と改善点の抽出」に関して考えてみましょう。
研修が本当に効果的なのかを測る研究は今も世界中でなされており、その方法には、報告書、アクションプランの作成、研修後アンケート、フォローアンケート(時間が経ってからのアンケート)、事後インタビューなどがありますが、その中で受講者アンケートは最も一般的な方法です。他の手法と比べた特徴として、受講直後に行うため、参加者の感情に関わる主観的・定性的な情報を得るのに向いています。
アメリカの経営学者のカークパトリック博士が提案した教育の評価法のモデルとして、4段階評価法を耳にしたことがある研修担当者は多いかもしれません。
- ①Reaction(教育研修内容の満足度)
- ②Learning(教育研修で何を学んだかという理解度)
- ③Behavior(教育研修による行動変容度)
- ④Result(教育研修内容が組織へ及ぼした影響度)
研修後のアンケートでは本来、上記①の「満足度」や、②の「理解度」を計測できることが期待されています。
ただし実際は満足度の計測に偏っているケースが多く、理解度についても計測するためには、アンケート形式を工夫する必要があります。
アンケートの設問を考える際のポイント
一般的な研修後アンケートの設問を考えるにあたっては、次のようなことに注意するとよいでしょう。
アンケートで何を知りたいかを意識する
「今後の研修内容を改善するため」であれば研修内容や進行についての評価、「現場での行動変容を促したい」のであれば気づき・今後の行動への影響を問う設問が必要です。
「満足度」だけに偏らない
「今日の研修に満足しましたか?」という問いは重要ではありますが、満足=効果ではありません。理解度についても測れる設問を用意しましょう。
客観的な設問と主観的な設問のバランスをとる
5段階評価などの客観的な指標だけでなく、「印象に残った点」「講師の印象」「もっと聞きたかったこと」など主観的な設問を加えることで質的な改善に活かせます。
抽象的な質問ばかりにしない
「わかりやすかった」「ためになった」などの曖昧な表現だけでは、何がよかった/悪かったのかがわからないため、「この研修を通じて、実践してみようと思ったことは何ですか?」のように具体的な行動や気づきに紐づけた設問を設けるとよいでしょう。
質問数を増やし過ぎない
質問が多いと、回答が雑になったり、最後まで回答されないこともあります。本当に知りたいことに絞って質問をしましょう。
研修タイプ別、アンケートの作り方例
ここからは、「理解度や意識の変化を測る」ための効果的なアンケートについて考えてみたいと思います。
重要なのは、研修の目的や望むゴールを念頭に、それがどの程度達成できたかを問う設問を用意することです。「目的」や「ゴール」は実施される研修によっても異なるはずです。そこで、よくある研修テーマごとに、想定される目的を踏まえつつ、研修後後アンケートのポイントを考えてみまししょう。
営業スキル研修
営業担当者向けのスキル研修では、一般に、「実務にすぐに活かせる」研修であることが求められます。
こうした研修では、「研修の内容が実務に役立つ内容だったのか」ということを、当事者の声として聞くことが有効です。
研修の時間配分、進め方の順序、スピード感が適切であったかどうかといった詳細な点もヒアリングしておけば、同様の研修を再度行う際、よりレベルアップした研修を実施できるようになります。
女性社員のキャリアデザイン研修
「女性」のように一定の層に向けて行われる種の研修では、学ぶ内容そのものに加え、「同じ立場にある人同士の意見交換で視野を広げてもらいたい」、女性社員なら女性社員同士の「社内ネットワークを広げる機会としたい」、該当する人たちの「要望を吸い上げたい」などの目的もあるはずです。
この場合、研修後アンケートでも、「他メンバーと交流できたか」、「自分にない考え方に触れることができたか」、「今後どのような研修や制度があるのが望ましいか」といったことを押さえておく必要があります。
コンプライアンス・ハラスメント対策
マネージャー向けコンプライアンス・ハラスメント対策研修の場合、「事例から予防と対策のためのポイントを学んでもらいたい」、「マネージャーとしての役割を理解してもらいたい」とうような点が目的となります。
つまり、提供された事例が「受講者の職場でも起こり得る内容だったか(リアルに感じられたか)」、研修を受講したあとで、「意識の変化はあったか」などという点が最も検証されるべき項目と言えます。
ロジカルシンキング研修(事前課題あり)
ロジカルシンキング研修では、事前課題で基本知識習得を課し、当日は演習を中心に実施するという手法がよく取られます。
この場合、基本知識の習得度合いが研修中に見えやすいので、事前課題についての意見もしっかりと聞き取る必要があります。事前課題が「理解しやすいものであったか」、「当日の演習の準備として適切であったか」、当日もっとパフォーマンスを出すには「他にどんなサポートがあればよかったと思うか」などをヒアリングするとよいでしょう。
研修の目的とゴールに合わせたアンケート設計を
こうして考えてみると、研修後アンケートを本当に有効なものとするためには、アンケート単体でどんな工夫するかだけでなく、「事前に研修の目的やゴールを明確にしておくこと」が重要だとお分かりいただけると思います。一つひとつの研修について、まずは目的やゴールを設定し、それに対応したアンケートを作成するという手順で、研修の振り返りをより的確なものに変えていきましょう。
JMAソリューションでは、JMA研修の目的やゴールの設定、研修後アンケートの設計も含め、お客様企業の課題に合わせた人材育成の全体像をご提案しています。詳しくは下記までお気軽にご相談ください。
https://event.jma.or.jp/solution_inquiry>>
<関連記事>



